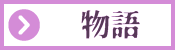バイバイ・シグナル01
お昼休みを告げるチャイムが鳴った。すぐさま食堂へかけていく男子、別のクラスから中学生時代の友達を探しに来る女子、それからお弁当を手に机に集まる男子女子。
この春、安代木高校に入学した相見亜矢はといえば、教室の向こうから手招きしてきた友人二人とともに、食堂へ廊下を歩きだしたところだった。
「ねー亜矢ちん、翔馬くんとは大丈夫?」
「えっ……なんで?」
話しかけてきたのは、中学生のころからの友達、みどりだった。亜矢は、開け放たれていた隣の教室のドアの向こうに翔馬の姿を探していたことに気づかれたのかと、驚いてして一瞬歩みを止めた。
「だって亜矢ちん、中学の時は翔馬くんと一緒に帰ったりしてたのに、高校入ってからそういうことしてなくない? 今日来る時も別々だったでしょ? お母さん亡くなって――」
「高校生にもなったらちょっとは羞恥心もつくもんだって。そうでしょ亜矢?」
一緒に歩いていた涼子は、深刻な口調になりかけたみどりを止めるように言って、亜矢の顔をのぞきこんだ。亜矢はちょっと笑顔を作ってうなずいた。
「うん、そんなとこかな。とにかく、大丈夫」
「そーゆーもん?」
「そうだよ、うちの弟なんて、うちが小六になったときにはすでに嫌がってた」
「えーっ、それはさすがに早くない?」
「そーゆーもんなんだって。ところでさ、さっきの授業だけど――」
それから話題は、翔馬――亜矢の双子の弟――のことからそれて、授業の話になって、それは食堂につくまで続いた。
亜矢と翔馬は、双子ということもあってか、それは仲のいい姉弟だった。中学生時代もそれぞれ別の部活に入っていても、しばしば一緒に登下校したものだ。
だが、高校に入ってから二人は一緒に登校することをやめた。
実際のところ、翔馬との関係は「大丈夫」などではなかったのだ。
亜矢と翔馬の母親が死んだのは、中学校の卒業式の日だった。
二人の父親は、二人が小さいときに死んでいて、亜矢の記憶の中に父親は存在しなかった。ずっと、亜矢と翔馬と母親の三人で暮らしていた。
「んじゃ、わたしは涼子たちとカラオケ行ってくるからー」
「おれ、章介んち行ってくんねー」
「はいはい、気をつけてらっしゃい。遅くならないようにね」
卒業式の後、亜矢は女友達と遊びに出かけ、翔馬は翔馬で友人の家に行っていた。
日が暮れたころ、亜矢の携帯電話に電話がかかってきた。叔母の友里恵からだった。
「友里恵さん、どうしたの?」
「とりあえず、一度帰ってきて」
亜矢が帰ると、家の周りに黄色いテープが張られていて、知らない人たちが家から出て行くところだった。
そして、家の中には友里恵が居て、知らない誰かと話をしていた。その誰かは、亜矢の姿を見ると会釈して家から出て行った。
「何があったの? 母さんは? それに、翔馬は? まだ帰ってないの?」
亜矢が尋ねると、友里恵は首を横に振った。
「落ち着いて聞いてちょうだい」
そのあと友里恵が話したことの意味を、亜矢はほとんど理解できなかった。
その時分かったのは、母親が殺されたのだということ、弟は母親を襲った誰かに連れて行かれたようだということ、これから亜矢は友里恵と暮らすということだけだった。友里恵は何かそれ以上のことを言いかけたが、あとは亜矢をそっとしておくことにして、ただ亜矢の肩を抱いた。
友里恵のおかげで、母親の葬式は実感を持てないまま、びっくりするぐらいあっさりと終わっていった。
そして、高校の入学式一週間前。三月も終わりが近づきソメイヨシノのつぼみが膨らみ始めたころ。
夕方五時のチャイムが鳴り響く、暮れ始めた街の中、赤信号の交差点の向こうに、亜矢は翔馬の姿を見た。道をふさぐようにあらわれた五人の人影。その真ん中に、翔馬は奇妙なローブをまとって立っていた。
「翔馬!? 翔馬なんでしょ!」
けれど、翔馬は亜矢の呼びかけに応えることはなかった。あるいは、その答えは車の走行音と街に響く五時のチャイムにかき消された。
確かに翔馬であったのに、こちらを見ている目は冷たかった。そして、片側二車線の道路を挟んだこちらとあちらで、永遠にも思えるほど見つめあったそう思った時、交差点をトラックが通過したその一瞬で、彼らの姿は翔馬もろとも消えていた。
「なんで、帰ってこないの? 何を、考えているの……!」
不安と寂しさに、居のあたりが震え、膝の力が抜けるのを感じた。
それから亜矢は、外に出るたびに翔馬の姿を探した。確かにどこかに、無事でいるはずだ。
亜矢と翔馬の母親が死んで三週間。時間だけが過ぎ、四月、入学式がやってきた。
亜矢と翔馬は同じ高校に入学するはずだった。そろいの制服に身を包んだ人々の中に立って、亜矢は翔馬の姿を探した。
(居るはずがない……)
そんな風に思っていた。それなのに、三つ隣の列の少し前の方に翔馬の後ろ姿が見えて、亜矢は目を見張った。信じられないくらい平然とした顔で、正面を見ていた。
そのまま、入学式は何事もなく終わった。
けれど、すべてが終わって帰ろうというとき、玄関で靴を履き替えると、
「亜矢」
不意に背後から声をかけられた。それも、肩のすぐ後ろから、囁くように。
亜矢は振り返りながら飛びのいた。翔馬だった。亜矢は、日暮れの交差点で見た不気味な姿を思い出し息をのんだが、そのあと心の中に湧き上がった不安とも怒りともつかない感情に任せてどなるように叫んだ。
「翔馬……。今までどこにいたの? なんで、帰ってこないの? なんで、ここにいるの!?」
「亜矢は、『絶対干渉能力』って知ってる? おれたちの中にあるもののことを。僕たちには世界を変える力があるんだ。信じられる? 信じられないよね」
その声は、昔の無邪気なままだった。そして不思議に落ち着いていた。けれど、目が笑っていない。ほら、と翔馬は掌を掲げて見せた。すると、その中心、掌の少し上のあたりにまがまがしい黒が、始めはただ小さなシミように、しかし見る間に拳ほどの大きさの球体となって現れた。
「おれは本当のことを全部聞いたよ。母さんたちがおれたちで何をしようとしてたか、亜矢はまだ知らないんだろ? おれたちは造られた子どもなんだ。世界を変える力を持つように、造られた子どもなんだよ」
「何なの、何を言っているの……?」
「おれたちなら、こんな世界、変えてしまえるんだよ。痛みも、悲しみも、何もかも消してしまえるんだ」
「何をバカなこと言ってるの?」
「これでも、バカだって言える?」
翔馬は、自分の掌の上の黒い球体を見つめて笑みを浮かべた。次の瞬間、黒い球は掌姿を消し、二人の間、靴箱の前に置かれたスノコの一部を覆うように現れたかと思うと、突風が吹いた。黒い球体が消えるとともに、スノコには円形に切り取られたかのような、穴が開いていた。
「え……?」
「こんなものじゃないよ。もっと大きなものだって、生きている人間だって、消して、損なってしまえる。そういう力さ」
背中を冷たいものが流れるのを感じた。
「おれなんだよ、亜矢。母さんを殺したのはおれだ」
無邪気なままの声が、恐ろしかった。
「う、そ」
亜矢は、翔馬の頬をはたこうと手を振り上げた。しかし、次の瞬間翔馬の姿は見えなくなった。
「残念だな。でもしょうがないや。またね。今度会う時は、亜矢を殺しに行くよ。そうすれば亜矢の力も、おれのものだ」
「私の……力?」
翔馬の姿はどこにもなかった。周りを見回してもどこにもいない。けれど、もっとおかしいのは、誰もそれに気づいた様子が無いことだった。亜矢は下唇を噛んで立ち尽くした。
「叔母さん、今日ね、翔馬に会った」
家に帰ると友里恵がいて、キッチンで洗い物をしていた。亜矢は開口一番そう言った。
「どこで?」
「学校。入学式に来てた。……叔母さん、何か知ってるの?」
驚いた様子を見せない友里恵を、亜矢はにらみつけた。友里恵は顔を曇らせると、洗い物の手を止めた。
「聞いたの?」
「母さんを殺したのは、翔馬だって。私たちは造られた子どもだって。世界を変える力ってどういう意味なの?」
「せめて亜矢は、このまま普通の女の子に、なんてやっぱり無理な願いね、姉さん……。わかったわ亜矢。全部話すから、ちょっと待って。座ってて」
バイバイ・シグナル02
テーブルを挟んで向かい合うように椅子に腰かけると、沈黙が二人を包んだ。そして、友里恵は大きく息を吐くと、口を開いた。
「どこから始めたらいいかしらね。二十年前、そう、あなたたちが生まれる前、私と姉さんは『アルカ』の一員だった。そこで私たちは、遺伝子物理学の研究をしていた繁幸さん、あなたのお父さんに出会ったの」
「『アルカ』?」
「世界を今のままにしておいてはいけないという思想の持ち主の集団、とでもしておいて。目的を達成するためには、過激な手段もいとわない、そういうところだった。あなたたちは、あなたたちの力は、繁幸さんの研究の成果なの。『絶対干渉能力』。世界の在り方に働きかけて、本来ありえない現象を引き起こす力よ。それが、生まれる前のあなたたちに埋め込まれた。というより、力を持たせた状態で、あなたたちの胚を発生させたというべきかしら。彼の能力は物質を無と交換する、ある種の空間転位。あなたの力はおそらく、存在の在り方を変える力。それで『アルカ』は世界を変えてしまおうと考えていた」
「母さんも?」
亜矢は、あまりにも壮大な話に身震いした。
「最初はそうだったはず。でも……あなたたちを愛してしまったのね。『アルカ』は、あなたたちを武器として育てることを望んでいた。だけど姉さんたちは、あなたたちを人間として育てようとしたの。それで、あなたたちが三歳の時、お父さんは殺された。表向きは事故だったけど、あれは制裁よ。組織に従わなかった者へのね。それで姉さんは、あなたたちを連れて逃げ出した。私は姉さんたちを始末するように命じられて、やっぱり逃げ出した愚か者よ。おそらく『アルカ』は私たちをすぐに見つけていたはず。でも、利用するつもりで生かしてたのね。姉さんも覚悟はしていたけど、まさか翔馬くんの力の目覚めに利用するなんて……」
「利用って?」
「干渉能力の発現には、ある程度の精神的ショックを与えるのが最適であると仮定されていたわ。おそらく、そのショックが『世界のために造られた』という事実であり、自ら母親を殺めることによって、能力を固着させたのではないかしらね……。姉さんを殺したのが、本当に翔馬くん自身であるとしたらの話だけれど」
「本当だと思う。あの時、翔馬はウソをついてなかった」
亜矢は、翔馬の表情を思い出すように目を閉じて、それからゆっくりとそう言った。なぜだか、その確信があった。
そんな亜矢の様子を見て、友里恵は驚いているというよりも、どこか悲しそうだった。
「そう、分かるのね……。おそらく、翔馬くんはあなたの力を奪うために、あなたを殺そうとするわ。彼の力は無と、あなたの力は存在とつながっている。彼の力は世界の脅威となるのに十分だけれど、本当の力は、あなたの力と一体になってこそ得られるものなの。本来あなたたちはひとりとして生まれてくるはずだったから」
「どうしたらいい?」
「今のあなたなら、きっと、もしもの時には自分自身を守るため力を使えるわ」
「でも私は、殺したくなんてない」
「あなたの力は、殺すためのものではないわ。ことが起こるまで、普通に生活しなさい。相手の出方をみましょう」
「そんなこと……できるの?」
「できる。そうやって姉さんも私も、ずっと生きてきたわ」
翔馬とクラスが別々になったのは、幸いだった。会うことさえ恐ろしいように思えたからだ。けれど、翔馬のクラスの前の廊下を歩く時、いつも教室の中に翔馬の姿を探そうと、視線を動かさずにはいられなかった。
そして、入学式から一週間もたたない頃、それはやはり夕方のことだった。何かが耳元を掠め、どこからか乾いた響きが聞こえた。そして目の前で何かがはじけた。全身鳥肌が立って、二発目に何が起こったか悟った。
銃。
そう思って、駆けだした瞬間何か、普通でないことが起こったのを感じた。一蹴りで、異常なほど高く飛び上がり、降り立つ衝撃はその跳躍に見合わない柔らかさだった。
「どういうつもりなの、翔馬ぁっ!」
その攻撃は確かに銃で、翔馬のあの消し飛ぶ黒い球体ではなかった。しかし、どこから狙われているのかさえ分からず、跳躍中に体をひねってあたりを見渡したものの、が結局逃げるので精いっぱいだった。
逃げ切って、亜矢は思った。
「わざと脅かして、こんな力使わせようとしたんだ……」
その日から、時折銃弾が亜矢に襲いかかるようになった。それはいつも夕方で、たいてい五時のチャイムが街に鳴り響く頃だった。
襲われるたびに、亜矢は自分の力を自覚していった。地面を蹴る力は強く、そして空中でさえ蹴りだすことが出来た。空中で想いのままに体勢を変え、普通の跳躍と変わりないくらい簡単に着地した。そしていつしか、自分を狙うものの姿を確認できるほどになった。
その日、亜矢は自分を狙うものの傍に翔馬の姿をみた。
銃弾をよけながら、翔馬の方へ向かって跳躍を繰り返した。歩道橋、ビルの非常階段やベランダの手すり、そういうものを伝っていく。
銃弾が掠めてほほが焼けるのを感じた。
震えるような思いを抱えて、それでも亜矢は止まらなかった。翔馬の姿に気を取られた亜矢は、銃弾が襲わなくなったことにも気付かなかった。
「翔馬!」
亜矢は、ビルの屋上に滑り込み、翔馬の肩をつかんだ。
「今度会う時は殺しに行く時だって言ったのに、亜矢の方からくるなんてね」
翔馬はニイっと笑って、右手を動かした。亜矢はそれを見て翔馬の肩を突き飛ばして身を引いた。そのまま亜矢は落下した。
落下しながら、さっきまで自分が立っていた場所が消滅するのを見た。翔馬の顔には、ただ不気味な笑みだけが浮かんでいた。
「狂ってる……」
着地して、亜矢はそのまま歩道のコンクリートに膝をつき、手をつき、へたり込んだ。涙がこみ上げてきて、亜矢は縮こまると嗚咽をもらした。翔馬の瞳の中に狂気が見えた気がした。そんな感覚を、現実と確信したのはその直後だった。
大きな音、何かがぶつかる音、砕ける音。亜矢がへたり込んだ地面から顔を上げると、胴にぽっかりと穴があいて崩落する建物が見えた。さっきまで翔馬が立っていた建物。それが、亜矢へ向かって倒れ、崩れ落ちてきていたのだ。
亜矢は息をのむと、掌で地面を強く押し、そのままの勢いで地を蹴って宙返りで車道の向こう側まで勢いよく跳躍した。次の瞬間、建物が完全に崩落した。
人々の悲鳴の向こうに、遠くサイレンが響いていた。
『本日午後五時十五分ごろ、雲雀沢市二丁目で爆発があり、二十階建てビルが倒壊しました。この爆発で、現在も数百人が――』
「爆発なんかじゃないよ」
亜矢はそう呟いてテレビを消した。そして、下唇を噛んでしばらく押し黙っていたが、顔を上げると英美理に告げた。
「叔母さん、わたし決めた。わたし、わたしが翔馬を止める」
「でも、どうやって?」
英美理の言葉の調子は、驚いているようでも困惑しているようでもなかった。ただ、亜矢がそう言いだすのを待っていたかのようだった。
「翔馬はもう、昔の翔馬じゃない。本気なんだ。わたしが止めなきゃ。だって翔馬はわたしの分身、双子の弟だもの。止めて見せる。たとえそのために、殺すことになるとしても」
ビルを倒壊させた日以降、翔馬は学校に姿を現さなくなった。
クラスが違っていたから始めは気がつかなかった。けれど、翔馬のクラスの前を通った時、前は見えた横顔が見えなくなっていて、気がついた。男の子たちの会話を聞いたところでは、どうやら風邪ということらしい。そのうち、亜矢の友人たちもその話を聞きつけて尋ねるようになった。
「よっす亜矢ちん、翔馬くんは今日も風邪かい?」
「おはよう、みどり。まーね」
「亜矢ったら、うつされないでよー」
「はいはい涼子。気をつけますっ」
そうやって他愛もない会話を、何でもないようにこなしながらも、亜矢は、ひそかにナイフを持ち歩くようになっていた。いざとなったら、翔馬を殺す覚悟を、亜矢は既に決めていた。
翔馬が学校に姿を現さないまま、数日が過ぎ、春の長雨に桜が散る頃。久しぶりの乾いた音が、投げ捨てられた水玉のビニール傘を射抜いた。亜矢は銃弾が傘を貫く前に、傘を手放し飛びのいていた。
「翔馬」
見上げたはるか先に、亜矢を狙う人々が見えた。見上げる亜矢に弾丸が降り注ぐ。亜矢はひたすらそれを交わしながら街を駆けた。翔馬の姿は見えなかった。
跳躍。
銃弾が髪を掠めて背後に消える。
亜矢の脚は宙を蹴り、歩道橋の欄干を蹴り、高層マンションのベランダを蹴り、高く高く上がっていった。銃弾が来る方向さえ分かるようで、亜矢はひたすらそちらへ向かって宙を駆けた。
「翔馬っ! もうこんなことやめなさい!」
そう叫びながら、亜矢の右手はポケットに忍ばせていたナイフをつかんでいた。
「言ったろ、亜矢。今度会う時は殺すって」
姿が見える前に聞こえた声は、驚くほどはっきりと亜矢の胸に届いた。はっとして思わず左の方を見ると、マンションのベランダに薄く笑う翔馬の姿が見えた。
何もない中空を蹴ると、亜矢は翔馬に飛びかかった。刹那、無が目の前を覆い尽くし、気がつくと二人は屋上に立っていた。
「人ん家で暴れるもんじゃないよ、亜矢」
「街ん中で撃ってくるあんたに言われたくない」
言葉は軽い調子だったが、二人の間には冷たい緊張が流れていた。銃弾はいつの間にか襲うのをやめていた。
「こんなことして一体何の意味があるっていうの? 世界を変えるとか、変えないとか、そんなことしたってどうにもならない!」
「いまさら、おれに帰って来いとでもいうつもり? いやだね」
亜矢は前方へ蹴りだし、その瞬間、亜矢の居た場所を黒い球体が覆った。空中で亜矢は下唇をかむと、ナイフを握りしめてそのまま翔馬の懐に飛び込んだ。
翔馬は目を見開いた。
そして、無が二人を覆った。
「よっす、涼子っち。おっはよー。あれ、亜矢ちんは?」
「おはよ、みどり。亜矢ならまだ来てないよー」
「んー、めずらしいなー。そういえば翔馬くんの方も、最近来てないよね?」
「そうだっけ? 二人してたちの悪い風邪にでもかかったんじゃない?」
「かなー? じゃーさ、部活見学終わりに一緒にお見舞い、いきましょか!」
「お、いいねいいね。じゃあ、そうしよ!」
朝のチャイムが鳴った。
バイバイ・シグナル03
目を開けると、そこは夕暮れに赤く染まる街。見覚えのある景色のようで、しかし見たことのない街並みが広がっていた。街路樹が緑色の枝を揺らしている。
「この、交差点……」
重く痛む頭に手を当て、ゆっくりと立ち上がると、亜矢はうめいた。見回すと、すぐそばに翔馬が倒れている。二人とも、交差点にほど近い歩道の上に居た。
翔馬の胸に、突き立てたはずのナイフは、まだ亜矢の手の中にあった。
「生きてる。わたしたち、二人とも生きてる……?」
降りかかる銃弾はなかった。襲いかかってくる人々の姿も無かった。
亜矢は、意識を失って横たわる翔馬の脇に膝をつくと、抱き上げようとするように肩に手を添え、状態を起こさせると、髪の毛をくしゃくしゃになでた。
「あんたはいったい、何をしたのさ」
翔馬は目を覚ましそうになかった。亜矢は泣き出しそうな気分になりながらも、どこかでほっとしている自分に気づいていた。翔馬が目を覚ましたら、きっと今度こそ殺してしまうことになると思ったから。
その時、亜矢に声をかける者がいた。
「君たち、大丈夫? 安代木高の制服だよね? びしょぬれだけど、どうしたの?」
サラリーマン風の姿をした若い男だった。
亜矢は、そう言われて初めて自分が濡れていることに気がついた。そういえば、さっきまで雨が降っていたのだった。それで桜が散ってしまった。
そこまで思いだして、息をのんだ。
夕暮れが綺麗に見える、晴れた空。そして、緑色の木々。
「今は……いつ」
間違いなく、先ほどまでと季節が違っていた。夏だ。
男は怪訝な顔をして、心配そうに亜矢の顔を覗き込んだ。
「交番か、病院まで、一緒に行こうか?」
亜矢は首を横に振った。
「大丈夫、だから」
亜矢はあわてて立ち上がろうとして、よろけた。男はとっさに亜矢の腕をつかんで支えた。
「なんなら、ほら、家においでよ。って、これじゃあ、なんか危ない男みたいだな……」
男は頭をぽりぽり掻いて、しばらく考え込んでいたかと思うと、携帯電話を取り出して、誰かと話し始めた。
「――だからさ、とにかく来てくれ。南町の交差点、そう、そこ――」
それから、しばらくしてやってきた一台の車は、どうやら男の知り合いのもののようだった。運転していたのは男と同じくらいの年の若い女。
「ま、どうしたの!?」
女はびしょぬれの亜矢たちを見ると、男の方を説明を求めるように見た。男が肩をすくめると、事情を聴くのは後回しと言わんばかりに、男に翔馬を車の後部座席に運ばせた。亜矢は助手席に座らされた。
「じゃあ頼むよ、英美理。僕もあんまり遅くならないようにするから」
「わかった、任せといて」
亜矢は、車の中で押し黙ったままでいた。気付いたのだ。英美理と呼ばれた女は、自分の母親の、若かりし頃であることに。
具体的に、いったい何が起こったのかは分からなかった。翔馬の能力は空間転位だと、いつか友里恵は言っていた。今度は時間さえも越えてしまったのだろう。亜矢はそう思った。
「じゃあ、あれが父さん……」
「ん?」
英美理は亜矢をちらりと見た。それから、気遣うようにバックミラー越しに後部座席の翔馬を見やった。
「何があったかとか、言いたくないかもしれないけどね、危ないことになってるなら、大人を頼りなさいよ?」
「……ありがとう、ございます」
亜矢は、自分の母親となるはずの人に、なんと言ったものかと逡巡して、やっとそれだけを言った。英美理はちょっと肩をすくめたけれど、気を悪くする風もなく車を走らせた。
「ただいま。悪いな、遅くなってしまって。あの子たちは?」
「寝かせたわ。男の子の方は、相変わらず眠ったままだけれど。とりあえず命には別状ないみたい」
「そうか。まあ、明日にでもちょっと話を聞けるといいんだが」
「ええ。あの地点なんでしょう? 異常な干渉振動が観測されたのは。だから警察にも届けなかった」
「ああ。あの子たちに何か関係があるはずだから。もしも、あの子たちが『絶対干渉能力』持っているんだとしたら、我々の計画は一気に進むぞ」
英美理のピンク色のパジャマを着せられた亜矢は、隣の部屋から聞こえてくる会話を、目を閉じたまま聞いていた。
自分たちが彼らの、目的のための子供であることが知られたらどうなってしまうのだろう。利用しようとするのだろうか。それとも、また――彼らにとっては「また」ではないが――守ろうとするのだろうか。
そんなことを考えているうちに、亜矢の意識は闇に落ちていった。
目が覚めると、英美理たちは家に居なかった。食卓の上にはラップに包まれた皿が二つと食パンの袋、それから一枚のメモがあった。
『仕事に行ってきます。温めて食べてね。 英美理』
亜矢は、ため息をつくと皿を包んだラップをつついた。中身は目玉焼きだった。
翔馬はまだ眠ったままだった。能力を使うということは、あるいはそういうことなのかもしれない。本来人間にできるはずのないことなのだから、自分の身を削ったとしても、不思議ではない。
(わたしも、あんなふうになっちゃうのかな)
亜矢は、目玉焼きを一人分だけ電子レンジで温めた。
「いただきます。母さん」
震える声でそう囁いて、目玉焼きを乗せた食パンにかぶりついた。誰もいない部屋で、一人で食卓について、亜矢は少しホッとしていた。
朝食を飲み込みながら、亜矢はこの状況をどうやり過ごすか考えた。このまま、何も語らずにこの時間で生き続けることは難しい。亜矢も翔馬も、まだこの時間には存在していない人間なのだ。戸籍もなにもない。未来に自分たちを生みだす英美理たちならば、あるいはそれを信じるかもしれない。だが、彼らに自分たちの存在が知れれば、結局元いた時間に起こったことと、何も変わらなくなってしまうだろう。
(どうしたらいい?)
亜矢は食べ終えた皿を洗い流し、もう一つの皿を冷蔵庫にしまった。冷蔵庫の扉を閉める瞬間、不意に一つの考えが頭をよぎった。
(自分たちが、生まれてこないことになれば、そうすれば、翔馬があんなことになったり、いろんなものが壊れて、傷ついたりしない……。でも、どうやって……?)
「ただいま。よかった、もしかしたら、昼のうちに出ていってしまうんじゃないかって、心配していたんだ。彼の方は、まだ目が覚めないみたいだね」
先に帰ってきたのは男、繁幸の方だった。
「そろそろ事情を話してもらえないか? 彼をこのままにしておくわけにもいかない。警察や病院が嫌なら、うちの会社のドクターに診てもらってもいい。でも……」
繁幸は諭すように言ったが、亜矢は押し黙ったまま下唇をかんだ。信じて何もかもを話してしまう気には、なれなかった。自分の父親であるとはいえ、相手にそのつもりはないし、亜矢自身も父親のことはほとんど覚えていなかったから。それに、彼が自分を彼らの計画のために利用したいと思っていることは分かっていたから。
何と答えたらいいのか分からなくて黙っている亜矢の肩に、繁幸は何も言わずに手を置いた。
そのとき、
「亜矢」
そう言ったのは、繁幸の水色のパジャマに身を包んだ翔馬だった。
寝室へ続く扉の前に立っている翔馬の姿を見て、どくん、と心臓が鳴るのを亜矢は感じた。
「翔馬……」
「ああ、よかった。目を覚ましたんだ――」
繁幸は微笑みかけて、亜矢と翔馬の間に流れる張り詰めた空気に気がついて口をつぐんだ。
翔馬は亜矢を冷たい目で見つめたまま、口元だけに笑みを浮かべた。そして、面白がっているような声で言った。
「本気で殺そうとするなんて、ひどいじゃないか、亜矢」
「今なら、やり直せるわ、翔馬。母さんたちが死んだ未来を、書きかえられる」
「そんな必要はないっ!」
翔馬が叫ぶと、黒い球が翔馬と亜矢との間に膨らんだ。何もかもを消し去ろうとする闇は、あっという間に亜矢を飲み込んだ。
(これで終わってしまうのならば、それでもいいかもしれない)
暗闇の中で、亜矢はぼんやりと考えをめぐらせた。
しかし、
「危ないっ!」
不意に声が暗闇を突き破って、亜矢は闇の中からはじき飛ばされた。次の瞬間、さっきまで立っていたはずの場所を闇が覆った。そして、闇にのまれて消えてゆく繁幸の姿が見えた。
「なんで……」
その問いに答えられるものは、すでに居なくなっていた。目の前を覆っていた闇は散り時りになって消えた。今、ここから居なくなったのか、それとも、もうどこにも居ないのか。どちらだろうかと、思ったとき、亜矢は体の感覚を失って倒れた。
「何を……したんだ」
亜矢と同様に崩れ落ちながら、かすれるような声で翔馬が言った。
「あんたが……やったのよ。やっぱり、あれは……父さんだった」
亜矢が絞り出すように言うと、翔馬は驚きに目を見開いた。その目には、涙が浮かんでいるように見えた。けれど、もう亜矢にはそれ以上何も考えることが出来なくなって、何も、見えなくなった。
「よっす、涼子っち」
「お疲れー、みどり」
「あれ、なんかさー、うちらどっか行く予定なかったっけ?」
「へ?」
「あれ、違ったっけ? 朝、そういう話した気がしてたんだけどな」
「そうだっけー? まあ、二人とも思いだせないってことはさ、大したことじゃなかったんだって」
「かなー?」
「そだよー。んじゃさー、帰りどっか寄ってかない?」
夕方五時のチャイムの音が遠くこだまして、消えていった。