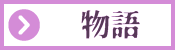空を飛んだら
それはとある冬のこと。寒い雪の平原に、カカシがひとつ立っていました。木の棒を組んで作られた体には着古された羽織と軍手。白い布地に顔の描かれた頭には笠をかぶせられていました。
カカシの役目は畑の作物を見守ることでした。なので、冬の間カカシには何もやることがありませんでした。とはいえどこかへ行くこともできず、カカシはずっとそこに立っていました。
あるとき、雪の降る中をひとりの男がやってきました。何もかも雪に隠れた平原にぽつりと立つカカシの方へ、男は近づいてきました。
「今日は本当に冷えますね」
男はカカシに話しかけながら、カカシの頭の笠の上に積もった雪を掃いました。
「ありがとうございます。たしかに今日はひどい雪ですね」
「本当にたまりませんね。しかし大変でしょう、こんなところにひとりで立っておられるのは」
「いえいえ。こうしているのがわたしの本分ですから。まだ遠くへいらっしゃるんですか」
「ええ。こんな雪の季節に出てきたことを、少し後悔してしまいますね。やはり歩いていても体に雪が積もるのは変わりませんから」
男は笑いながら答えた。
「それでしたら、わたしの笠をもっていくといいですよ」
「しかしそれではあなたが濡れてしまうのでは」
「わたしなど所詮は木と藁でできた人形。笠などは飾りです。濡れてもあなたほど困りはしませんよ。風邪をひくこともない」
それに、とカカシはいいました。
「暖かくなって、もしもわたしに笠が必要になるのなら、畑の主がまたかぶせてくれるでしょう」
「本当にそれでよいのですか?」
「ええ」
「それでは」
男はカカシの頭からそっと笠を外し、それをかぶりました。そして、ほほ笑むと礼を言いました。
「助かりますよカカシ殿。それではそろそろわたしはまいります」
「どうぞ御気をつけて。わたしの方こそ、話し相手になっていただき楽しかったです」
男は礼をして、再び雪の上を歩いて行きました。
それから何日か経って、今度は風の強い日のことでした。その日は雪は降っていませんでしたが北からの冷たい風が、平原を絶え間なく駆け抜けていました。
そんなとき、老女がやってくるのが見えました。今度は男が来たのとは反対側からです。そして、老女もカカシの方へやって来ました。
「今日は本当に冷えますねえ」
老女はカカシに声をかけました。
「ええ本当に。今日はとても風が強いですね」
「わたしなど途中で肩かけを風に持っていかれてしまいましたよ」
老女は寒そうに肩をさすりました。
「それは大変だ」
「まあねえ、本当に強い風でしたから。しかたありませんね」
「しかしそれでは冷えておしまいになるでしょう。わたしの羽織などでよろしければ、お使いくださいな」
「そういうわけにはいきませんよ」
「わたしなど所詮は木と藁でできた人形。羽織などは飾りです。なくなってもあなたほど困りはしませんよ。風邪をひくこともない」
「助かりますよカカシさん。それではそろそろわたしは行かないと」
「どうぞ御気をつけて。話し相手になっていただき楽しかったです」
「わたしもこのようなところでお話しできるとは思っていませんでした」
老女はそういうと、深くカカシにお辞儀して再び雪の上を歩き始めました。
それからまたしばらくしたころ。その日は雪も風も止んで。ただやっぱり寒い日でした。
今度はひとりの少女がやってきます。
「今日は本当に冷えますね」
少女はカカシに声をかけました。
「ええ本当に。しかし、見たところあなたはずいぶん薄着のようですが、寒くは無いのですか」
カカシの言うとおり、少女はまるで真夏のように羽根のついた麦わら帽子に短い袖のチュニック、それからひざ丈のパンツをはいていました。足元はかろうじてブーツです。
「ありがとう。わたしなら大丈夫ですよ。でも、そうですね……。少し手が冷たいかしら」
「それならどうぞわたしの手袋をお使いくださいな。少しけばだってはおりますが、きっと暖かいですよ」
少女は断りましたが、最後にはカカシから手袋を受け取りました。そうしてカカシはすっかり芯と腕の棒、それから布を巻いた顔だけの寂しい姿になってしまいました。
「貰うばかりでは申し訳ないですね。代わりに、この帽子を差し上げましょう」
少女は自分のかぶっている羽根のついたかわいらしい帽子をカカシの頭にかぶせました。
「これは、魔法の帽子です。これをかぶっている限り、あなたは自由に空を飛び、どこにでも行くことができます」
「そんなすばらしいものを、わたしなどがもらうわけにはいきませんよ」
「いいえ、わたしにはあなたから頂いた手袋がありますから。それに二本の足と靴があるかぎり、わたしはどこへも自由に行けるのです」
「しかし……」
カカシが誰かから何かをもらうなんて、初めて作ってもらったあの夏以来です。だから、カカシは戸惑いました。
「さあ、飛んでみたい、飛んでゆきたいと願ってみてください」
少女はそんなカカシを笑顔で促します。
カカシはおそるおそる、少女に言われた通りにしてみました。すると、体がグイっと上の方へ持ち上げられるのが分かりました。そして、ついに体が地面から抜けたのです。
「好きなところへお行きなさい。でも、あまり長く飛びすぎないように気をつけて。落ちてしまうから。落ちても危なくないように、あまり高く飛ばないでくださいね」
「ありがとう。行ってみます」
カカシの声は本当にうれしそうでした。なぜって、生まれて初めてここではない場所に行けるのです。見たことのない景色を見られるのだ、あったこともない人と話せるのだ、そう思うとカカシの心は躍りました。
「春には戻ってきてくださいね。きっとあなたの作り主があなたを必要とします」
少女はカカシを見上げて言いました。
「もちろん。仕事がはじまるまでには帰ってきますよ」
カカシは少女に礼するように体を傾けると、空高く浮かび上がり、そして遠くに見える山の方へと飛んでゆきました。
カカシは高く、遠くへ飛んでいました。初めのうち、見下ろす景色は一面真っ白でしたが、ずっと飛んでいくとその景色から雪が無くなり、緑が現れ、そしてその緑がだんだん濃くなってゆきました。カカシが居る辺りはもう夏のようでした。けれども、強い日差しにあってもカカシは気にしません。少女にもらった帽子が日差しを遮ってくれていますから。
見下ろす景色の美しさに見惚れ、カカシはどれほど飛んだのか分からないくらい長い間飛んでいました。そして、少女の忠告も忘れて高く高く昇って行きました。
そしてある時。突然カカシの体が揺れました。そして、糸が切れたかのように落下し始めたのです。
「うわあ!」
カカシの頭には、まだ確かにあの帽子が乗っていました。それなのに、今その帽子にはカカシを持ち上げる力が無かったのです。長く飛びすぎると落ちる、という言葉の意味が初めてわかりました。そして、カカシはもみ殻の詰まった重い頭を下にして、まっさかさまに下へ下へと落ちていきました。
ざぶん!
それはとある夏のこと。森の中にある小さな湖のほとりに、河童が一匹寝ころんでいました。
すると、上の方から「うわあ!」という声が落ちてきました。河童がおや、と思って目を開けると、ざぶん! と、湖に何かが落ちました。
見ると、太い木の枝のようなものが、ごぼごぼと水の中に沈んでいくのが分かりました。
(なんだあ、木の枝か)
河童は再び目を閉じ寝ころびました。しかし、
(あれ……『うわあ』?)
声が聞こえたことを思い出すと、河童は飛び起きました。そして、あわてて水の中にするりと飛び込みました。
水の中で下の方を見ると、ごぼごぼと沈んでいく十字の木の枝が見えました。よく見ると白い頭のようなものが付いているようです。
(何だろう、あれは)
河童は、生まれてからずっと湖のそばを離れたことがありませんでしたから、カカシのことなんて知りませんでした。けれど、落ちてくるときに叫んでいたのだから、助けなくては大変と、その木の腕を掴んで水面までひっぱりあげたのでした。
「うーん、重いなあ」
そうして、たっぷり水を吸って重くなったカカシを引きずりながら、よく陽のあたる乾いた地面まで連れて行きました。
「おーい。大丈夫かい」
河童はカカシの白い頭をぺたぺたと叩きました。
「おーい。せっかくひっぱりあげてあげたのに、話し相手にもなってくれないんじゃあんまりじゃないか」
河童はつついたり、ひっぱったりしてなんとか起こそうとしました。すると、
「うーん。いてててて」
湿っぽいもごもごとした声が聞こえてきました。
「あ、よかった。気がついたんだね」
「おや、あなたは……?」
カカシは重たく湿った体を動かすことができませんでしたから、地面に倒れたまま言いました。
「僕は河童だよ。この湖に住んでいるのさ。君はいったい何なんだい? 初めは木の枝かと思ったけど、よく見ると、少しヒトに似ているね」
「わたしはカカシです。木と藁でできた人形ですよ」
河童は分かったような、分からなかったような顔をして、それから尋ねました。
「なんで空から落ちてきたの?」
それは、とカカシは答えかけて、はっとしました。
「わたしの頭に、帽子はついていますか?」
「んー? あるよ、あるよ」
「それはよかった。この帽子は魔法の帽子で、かぶっていると空を飛べるようになるのです。親切な方から頂いたのですが、わたしは飛びすぎると落ちてしまうという忠告を忘れて、少し飛びすぎてしまったために落ちてしまったようなのです」
少しほっとしたような、悲しそうな声でカカシは答えました。もう二度と飛べなくなってしまっていたらどうしよう。どうやって帰ったらいいのだろう、と考えていました。
「へーえ。それで空から。いいなあ、空を飛ぶってどんな気持ちだろう。ずっと遠くから来たんだろう?」
河童は夢見るようなまなざしで、空を見上げました。
「ええ。あなたもどこか遠くへ行きたいのですか?」
「うん! ……でも、僕はこの湖からあまり遠くへはいけないんだ。いけるとしても、雨が降った日じゃないと」
「どうしてですか」
「ほら、僕は体が乾くと死んじゃうから。水辺からあまり遠くに離れられないんだよ。川をたどればいいんだけどね、最近はこの湖に流れ込んでくる川の水かさが減っちゃったんだ。雨が降ったあとじゃないとまともに水が流れない。今年は雪解け水も少なかったからね。夏になったら湖も干上がっちゃうんじゃないかって、戦々恐々だよ」
河童はさみしい気持ちになってうなだれました。もしも本当に干上がってしまったら、河童が暮らせるところは無くなってしまうでしょう。
「そうなのですか……。何かわたしにできることはありませんか? 今はこのような有様ですが、体が乾けばきっとあなたの助けになれるでしょう」
「ありがとう。でもお天気ばかりはどうにもならないよ」
河童がそう言った時でした。
「わー、河童くん。それどうしたんだあ」
空から誰かが河童に声をかけました。見上げると黒い鳥が一匹、空をくるくると回っています。
「やあ、カラスくん。こちらは、えーっと。……カカシさんだよ。湖に落ちたのを助けたんだ」
カラスはぱたぱたと降りてきて、好奇心旺盛な黒い瞳をくりくりさせて、カカシに近づくとつっつきました。
「いてっ。突っつかないでください」
「わお。動いた、しゃべった!」
カラスは少し驚いたように羽ばたいて、カカシから離れると首をひねりました。
「でもどうしてカカシがこんなところに?」
「空飛ぶ帽子で飛んできたのですが、落ちてしまいまして」
「へえ。カカシも空を飛ぶんだ?」
おかしそうにカラスは翼を震わせました。
「河童さんとカラスさんはお友達なのですか」
「うん」「まあな」
「ではカラスさん。河童さんを助けてあげる方法、何か思いつきませんか」
「助けるって、何の話だ?」
「このまま雨が少ないままだと、この湖が干上がってしまうかもしれないんです」
「へえ、そのことか」
「カカシさん。気持ちは嬉しいけど、お天気はどうにもならないよ」
河童はちょっと笑って困ったように言いました。けれど、
「まあ、雨降らせるくらいならなあ」
カラスはそうつぶやいたのです。
「え?」
「ああ、いや。雨雲のところくらいまで飛べればな、話しつけることくらいできるかもしれないな、と」
「本当ですか! ああ、でもわたしは今は飛べないんでした」
乾き始めたカカシの声は明るくなっていましたが、すぐにまた湿っぽくなってしまいました。
「それにあまり飛んではいけないんじゃなかったけ」
さらに河童がそう言ったので、さらにカカシはしょんぼりしてしまいます。
「はい。……残念です。命の恩人にお返しができないというのは」
「やだなあ、命の恩人だなんて。あんまり気にしないでよ」
河童は元気づけるように、ぺたぺたとカカシの腕を叩きました。
「律儀なやつだなあ。あとで仲間に言っとこうかな」
その様子を見ていたカラスは興味深げに首をかしげ、そう言いました。
「何をですか?」
「カカシはたいそう律儀なやつだから、あんまり怖がんなくてもいいって」
「ダメですよ。わたしは任された仕事は果たしますからね」
「なんだあ」
カラスは少し残念そうにつぶやくと、翼を広げて空へ舞い上がりました。
「あ、もういっちゃうんだ」
「また来るよー!」
カラスはそれだけ言い残すと、高く高く飛んで行き、すぐに木々の間に隠れて見えなくなりました。
「悪いことを言ってしまったでしょうか」
「なんで? ……ああ、カラスくんは別に君が何か言ったから飛んでったわけじゃないよ。ほら、もう太陽の光が黄色くなってるだろう」
なぜかしょんぼりしているカカシに、河童は空を指差し言いました。
言われてみれば、空の色は心なしか黄色がかっているようです。
「カラスくんは、夕暮れまでに山に帰らなくちゃいけないからね」
「帰る、ですか……」
その時カカシはあの雪原のことを思い出していました。
あそこではまだ雪が降っているでしょうか。帽子をくれた少女は「春には戻ってきてくださいね」と言っていました。畑がはじまるころには帰らなくてはいけません。
「カカシさん?」
「いえ。わたしも帰らなくてはならないところがあるのですが、帰ることはできるのだろうか、と」
河童は少し驚いたような、悲しそうな顔をしました。それからこう言いました。
「きっとまた飛べるよ。その帽子がまた君を飛してくれるまで、ここにいたらいいさ。僕は君が居ても気にしないもの」
そして、河童は湖にするりと飛び込み、水面に顔だけ出して続けました。
「むしろ、新しい話し相手ができて僕は嬉しいのさ」
そして、カカシが河童の住む湖に落ちてから三日目の昼下がりのこと。
「あ!」
初夏の日差しにすっかり乾燥したカカシは、小さく驚きの声をあげました。
「立ってる! 飛べるようになったんだね」
水面から顔を出した河童がうれしそうに言いました。
「はい。正確には浮けるようになった、ですが」
カカシは頭を上にして立っていました。乾いて軽くなったからなのか、帽子の調子が戻ってきたからなのかはわかりませんでしたが、帽子はカカシの体を持ち上げられるようになっていたのです。
「飛べないの?」
河童は好奇心いっぱいの瞳をキラキラさせてカカシを見つめましたが、カカシは体を左右に小さく回転させて否定の意を示しました。
「これが限界みたいです。でも動けるだけで随分良いものですね」
カカシがするすると草の上を滑るように動き回って見せると、
「おー!」
頭上から声が降ってきました。カラスです。
「立ってるじゃーん」
「うわっ」
カラスが左腕に止まったので、カカシはバランスを崩しそうになってぐらぐら揺れました。
「あ、ごめん」
「いえ。もう大丈夫ですよ」
その言葉の通り、ぐらぐらは小さくなってまた元通り、カカシはまっすぐに立っていました。
「ってことはもう飛べんのか?」
「まだ無理みたいです」
「ふーん。そいつは残念。前にさ、雨を降らせるのがどうって話したの覚えてるか?」
「え? あー」
ふたりは一瞬キョトンとしましたが、思い出しました。
「雨を降らせるくらいならって言ってましたっけ」
「そうそれ。カカシくんが飛べるようになるならさ、なんとかなるかもしれないよ」
「本当ですか?」
「まあ、あちらさんの気分次第だけど」
そう言って、カラスは綺麗に晴れた空を見上げました。
「あちらさん?」
つられて上を向いた河童が、首をかしげました。
「雨雲さんだよ」
カラスが言いました。
「え。でもそれは……」
河童は難しい顔をしました。
「雨雲さん、ですか?」
「そう、雨を降らせると言ったらあのお方。直談判すればなんとかなるかもね」
「でも、それならカラスさんにもできるのでは」
「無理だよ。無理」
答えたのは河童でした。
「カラスくんには雨雲さんとの良くない思い出があるんだ。だよね?」
カラスは肩をすくめました。
「悪い思い出?」
「昔、雨雲さんのそばをかすめたときに殺されかけた」
「タイミングが悪かったんだよ。ちょうど稲妻を放とうっていうその瞬間にそばに寄るから」
「だけど焦げたんだぞ! 尻尾の先が」
「別に雨雲さんが悪いわけじゃないだろう」
「分かりました!」
河童とカラスが言い合っていると、突然カカシが元気よく言いました。
「ちゃんと飛べるようになったら、わたしが雨雲さんに話をしてみます」
空に少し雲が出ている、けれども晴れた日のことでした。
「本当に行くのかい? もしも雨雲さんが稲妻をいっぱい持っていたなら、無理せず戻ってきてよ」
すっかり飛べるようになったカカシは、カラスの言っていた雨雲のもとへ行こうとしていました。
「はい。ありがとうございます。それじゃあ行ってきます!」
その言葉とともに、カカシは勢いよく空へ飛びあがりました。
「いってらっしゃい」
河童の声を背に、カカシは昇っていきました。どんどん昇っていくと、綺麗に整列して飛んでゆく鳥の群れが声をかけられました。
「こんにちは。こんなところで何をしているの」
「こんにちは。雨雲さんに会いに行くところです」
「そしたら、もう少し昇っていくといいよ。気をつけてね」
それからどれくらいたったでしょう。カカシはどれくらい昇ってきただろうかと、大地を見下ろしました。そこには広大な森が広がっていて、その向こうにある平原や、山々が青く見えていました。そして、河童のいる湖はというと、広大な森の中の小さな煌めきに過ぎなくなっていました。
それから、カカシはさらに昇っていきます。すると今度は、ぽっかり浮かんだ白い綿雲が声をかけました。
「こんにちは。こんなところで何をしているのかな」
「こんにちは。雨雲さんに会いに行くところです」
「そうしたら、あとちょっとだよ。あっちにある灰色のが雨雲さんだから。でも気をつけてね」
にょきっと腕を生やして示してくれた綿雲にカカシは感謝して、空に広がる灰色の一角へ向かいました。
近づいてみると、雨雲の灰色の体からは、時折青っぽい光がちらちらと見えました。カカシはそれが稲妻なのだろうと思いましたが、声が聞こえるところまでは、と雨雲に近づいて行きました。
さらに近づいてみると、そこでは小雨がふっていました。早くしないと濡れて、重たくなってしまいます。カカシはあわてて叫ぶようにいました。
「雨雲さん、こんにちは!」
「おや、どなたかな」
重たく湿っぽい声で、雨雲は言いました。その声に合わせて稲妻が躍ります。
「わたしはカカシです。雨雲さんにお願いがあってここまで来たのです。わっ!」
その時、小さな稲妻がひとつカカシのそばを落ちて行きました。
「ああ、これは失礼。だが話なら急いでおくれ。もうすぐわたしの下は雷雨になる」
雨雲はのんびりとした口調で、カカシにそう言いました。
カカシは急いで、河童の湖の話をしました。
「だから、もっとたくさん雨を降らせてほしいのです」
必死に語りかけるカカシの言葉に、雨雲はうんうんとうなずきました。
「そうかそうか。あの森の辺りは雨が足らんのか。雨くらい降らせてやってもいいがな。しかしたくさん降ればよいというものでもなかろう。まあ、考えておいてやるから、今は早く帰りなさい」
そう言ったそばから、稲妻が落ちていきます。
湿って重くなってきたことに気づいたカカシは、雨雲に言われた通り帰ることにしました。
「ありがとうございます。よろしくお願いします」
無事に雨雲のそばを離れたカカシでしたが、帽子のことが心配になってきました。前に落ちた時よりも、少し高い場所を飛んでいるような気がしたからです。飛んだ距離はずっと短かったので油断していましたが、もしかしたら河童のところへ着く前に、また落ちてしまうのではないかと不安になりました。けれど、カカシは決してスピードを上げません。あまりはスピードを出して、帽子に余計な負担がかかると思ったのです。カカシはむしろゆったりと飛んで行きました。
しかし、そんなカカシの努力もむなしく、
「わっ」
カカシの体がガクンと揺れました。前回のように一気に落ちたわけではありませんが、カカシの意思に反して高度が下がり始めています。
「大変だ!」
とはいえ、もはや思い通りになるのは進む方向だけでしたので、ひたすらあの森の湖のあるあたりを目指して飛ぶしかありませんでした。
ようやく森の上にたどり着いた時には、もう木にぶつかりそうなくらいまで高度が下がっていました。帽子にしてみれば、もう飛んでいるのが奇跡みたいなものでした。そして、
「うわあ!」
ぷつんと糸が切れたかのように、浮力が消えました。
「大変! 大変!」
カラスが叫びながら湖へやってきました。
「どうしたの?」
湖の縁で寝ころんでいた河童は、ただならぬ空気を感じ飛び起きました。
「さっき仲間から聞いたんだ。カカシくんが落ちるのを見たって!」
「なんだって?」
カラスと河童が森を抜けてゆくと、カカシは木々の間に倒れているのが見えました。体の周りには落ちてくる時に一緒に連れてきた木葉や細い枝が散乱していて、そばにはあの羽のついた帽子が転がっていました。
「カカシさん! カカシさん生きてる?」
「うう。河童さん、ですか?」
くぐもった声が聞こえました。
「大丈夫?」
河童はカカシのわきにしゃがみ込むと、心配そうに言いました。カラスもぱたぱたとその傍に降り立って、心配そうに見つめました。
「ええ。あの、体をひっくり返していただけませんか。――雨雲さんは、なんとかしてくださるそうです」
河童に体を仰向けにしてもらうと、カカシは嬉しそうな声でそう言いました。すると、
「うわーん。カカシさん」
河童はがしっとカカシを抱きしめて、ぽろぽろと涙をこぼし始めました。
「ったく、おかしなやつら」
カラスの目がキラッと光りました。それから、帽子のところまで飛んでいくと、それをくわえてカカシのところまで持ってきて、顔の上に落としました。
「帽子、落ちてたぞ」
「あ、すみません」
帽子を顔の上に落とされても、なお変わらない調子でしゃべるカカシを見て、カラスはいきなり翼をばたつかせました。
「あー、もう! どうしてお前はそんなんなんだ。あーなんかこう、丁寧っていうか。もう! もっと自分を大事にしろよう」
目は涙でキラキラ光っています。
「え?」
カカシは突然の出来事に驚き、言葉が出ません。すると、河童が涙をぬぐって説明しました。
「カラスくんは君のことが心配だったのさ。自分が余計なことを言ったせいで、死んでしまったらどうしよう。自分の方が絶対うまく飛べるのに、どうして自分でいかなかったんだろう、って」
河童はカカシの顔から帽子をどけてやると、震えるカラスの翼をなでました。
「そうだったんですか。ありがとうございます、カラスさん」
カカシはやさしく言いました。
「誰かのために自分を犠牲にするなんて、なしだぞ」
「そんなこと、思っていませんよ」
「だって、危ないからいやだって言ってるそばから、お前ときたら! なんだって、そんな風に……」
カラスの声は震えていました。
「そう、ですね。わたしは、わたしにできることをやりたかったのだと思います。いままでわたしはずっと、動くこともできなくて、できることなんて本当にわずかでしたから。もっといろいろなことをやってみたかった。それが誰かの役に立つなら、やってみたかったんです」
カラスの言葉に息をのんだカカシの答えは、何かを確かめるかのようにゆっくりとしていました。
「犠牲になるつもりなんてなかったんですよ。でもそう見えたのなら……ごめんなさい。これからはもう少し気をつけます」
カラスは鼻をすすって、身震いすると翼をなで続ける河童の手をふりはらいました。河童はそんなカラスとカカシを見比べて、うれしそうにほほ笑みました。
それはとある昼のこと。森の中にある小さな湖のほとりに、カカシが一本と河童が一匹、それからカラスが一羽おりました。彼らがいつものように楽しそうに話をしていると、どこからか金属を打ち鳴らしたような音がしました。
「もうあちらでは、雪解けですよ」
振り向いたカカシたちの前に、少女が立っていました。それは、あの冬の平原でカカシに空飛ぶ帽子を渡した少女でした。
「あなたは……どうして?」
「二本の足と靴さえあれば、どこへでも行けると言ったでしょう」
驚きを隠せないカカシに、少女はほほ笑みかけました。河童とカラスはわけが分からない様子で、ただ唖然としています。
「君は誰なんだ?」
「わたしはその帽子のもともとの持ち主です」
少女はカカシの頭を指して言いました。
「そうなの?」
「はい。あの、すみません。わたしはもう飛べないのです」
カカシは申し訳なさそうに、小さな声で少女に言いました。すると少女は驚いた風でもなく、やさしく答えます。
「飛びすぎてしまったようですね。それにきっと、高く高く飛んだのでしょう? でも、二度と飛べないというわけではありませんよ。いずれ時が来ればまた、その帽子は力を取り戻し、あなたを運べるようになるでしょう」
「本当ですか! ……でも、約束は果たせませんね。春には戻るという約束は」
「帰りたいという気持ちはあるのですか?」
少女は少し驚いたように首をかしげました。
「もちろんです!」
「あの平原に、連れて行ってさしあげることはできます。でも、そうしたらこちらに戻ることはできなくなるかもしれません。その帽子が力を取り戻すという保証はないのです」
そう言って、少女は河童とカラスの方に目をやりました。
「いってしまうのかい?」
河童はおずおずと言いました。
「……はい。必ず帰ると決めていましたから」
カカシは一瞬ためらいましたが、発した言葉はゆるぎないものでした。
「一緒に行きたいなあ」
「ダメですよ、河童さん。あの平原には大きな川も、湖もありません。それにせっかくこの湖が――」
湖は、最近頻繁に降るようになった雨のおかげでうるおっていました。
「分かっているよ」
「あはは、じゃあ僕はときどき君のところに遊びに行こうかな」
カラスはぱたぱたとカカシの周りを飛びながら笑いました。
「作物を荒らさないでくださいね」
「もちろん」
真面目な声を出したカカシに、カラスもいつになく真面目な声を出して返しました。それを聞いた河童が吹き出すと、カカシも笑い、真面目な顔を保とうとしていたカラスもつられて笑い出しました。少女はそれを幸せそうな表情で見守りました。そして、笑いが鎮まると尋ねました。
「よろしいですか?」
カカシは河童とカラスの顔をうかがい、それから少女にうなずきました。
「では」
少女は右腕をカカシの腕の下に入れ、抱えるようにすると、ブーツのかかとを一回強く打ち合わせました。金属を打ち鳴らしたような、気持ちのいい響きが聞こえて、カカシと少女の姿はもう見えなくなっていました。
それから、カカシが河童と出会うことはもう二度となかったそうです。
けれど、カカシが立っているあの平原では、カラスをよく見かけるようになったといいます。