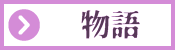祭壇の棺
何百年もの時を生きた無数の木々が、苔むした大地に根を下ろしていた。天高く広げた枝は青い葉を抱え、雨粒を集めては滴らせた。
柔らかく湿った巨木の幹の間、飛び跳ねるように歩く子供がいた。大地にうねる木々の根を踏まぬように、傷つけぬように、その子供は素足で注意深く、しかし軽やかに森を進んだ。
ここは死の森。しかし、森を行くジュンナには、未だそれは実感を伴わない事実にすぎなかった。彼女には、あるべき〈根〉がなかったから。
この森の話をしよう。ここは広大な森が、人々の知る限り永遠に広がっている場所だった。樹齢何百年もの、立派な大木ばかりが、空に枝葉を伸ばしていた。
この森で、〈人〉とは木々の根の間から生まれてくるもののことを言った。胎児は樹木の根の股に発生し、〈母なる木〉との絆を〈根〉で結んだまま生まれおちる。そして、〈母なる木〉から得る知識に守られて、大人になっていく。成人の年齢になると、人は〈根〉を切り、あるいは絆を結んだまま、森の木々を慈しんだ。人はそのために存在した。森が人を育み、人が森を育む。それがこの世界だった。
あるとき、人々は、木々のように緩やかに老いながらも、長く長く引き伸ばされたように生き続けていることに気がついた。死が無くなった、ということに。森の木々たちもまた、一本たりとも、枯れ倒れることはなくなった。木々が、森が、ここにあったはずの、あらゆる死を拒み、捨てたのだ。
天井も地表も、深緑に覆われた世界。それは、命あふれる場所のように見えたかもしれない。だが、大地に根付くのは、今や老木ばかり。大地に落ちる種子も無く、巨木の広い枝葉に光を遮られては、かつて落とされた種子たちも、芽吹くことなど叶わなかった。老いすぎた木々は、人を孕むこともなくなった。
古い木々たちは、ただそこに在り続けるだけ。何百年もの長い間、新たな誕生の喜びを見ぬまま、人々はただ変わることのない時を過ごしてた。
そんな時現れた、新たな子供がジュンナだった。
〈森守りの媼〉のエルは、〈母なる木〉と繋がる〈根〉を通して、木々から森の中に現れた異質な命の存在を告げられた。〈根〉から伝わる木々の感覚を頼りに、命のあるところへと向かうと、そこにはまだ歩けるようになったばかりの、小さな赤ん坊が転がっていた。
その姿を見て、エルは目を見張った。彼女には、人ならばあるはずの〈根〉がなかった。切られたわけではなく、まるで元から存在しなかったように。
エルは〈根なし〉の赤ん坊を拾い帰り、ジュンナと名づけた。人々は、〈根〉を持たぬ彼女を恐れた。〈根〉を失った赤ん坊が、生きていられるはずがない。ましてや、木との絆なしに生まれる命などあるはずがない。そう、人々にとって彼女は死人と同じ、生まれてくるはずもない命だったから。
だが、エルはジュンナをごく普通に育て、ジュンナもまた、ほとんど普通に育っていった。言葉の覚えは少し遅く、体も大きくはならなかった。だが、媼には、ジュンナが普通の子供とあまり変わりないように見えた。けれどある時、媼は〈根なし〉の子どもと普通の子供との間の、決定的な違いに気がついた。
それは、ジュンナが言葉を話すようになった頃。森の深く、ひと際老いた木々が、その根を地表でうねらせ、枝葉が空の光を薄く透かすあたりに来た時だった。
「うわあ、キレイね」
ジュンナは緑色の天井を見上げて言った。顔には無邪気な笑みを浮かべて。
その様子を見て、エルは首をかしげた。
「そう?」
「うん! とってもキレイ!」
エルにとって、そこは憂いの震える場所だった。老いた木々の嘆きが、〈根〉を通して聞こえていたから。その葉を通す光も、根のうねりも、ただ悲しいばかりだった。けれど、ジュンナの顔にその憂いの影はなかった。彼女には〈根〉がないから。悲しみが聞こえないから。
「そう。お前には、これが美しく見えるんだね」
そういって頭をなでてやりながら、エルの頭は思った。この子供は、森の運命を変えるのかもしれない、と。
時が過ぎ、ジュンナは〈根切り〉の年齢、すなわち成人の年齢を迎えていた。
〈母なる木〉に守られずとも生きられるようになったもの、つまり成人を迎えたものは、〈母〉と決別し一人の人として生きるか、森との絆を繋ぎ続け森の意思の中に生きるかを、選ぶことが出来た。それが〈根切り〉、人として、改めて森に迎え入れられるための儀式だった。
ジュンナは、大地にうねる木々の根を踏まぬように、傷つけぬように、苔むした大地を〈根切り〉の儀式の祭壇へ急いでいた。
森の中心近くに、丸く開けた空間があった。そこにだけは、太陽の光が細く差し込んでいた。そしてその光が差す先には、真っ白な四角い祭壇が大地に半ば埋まるように座っていた。祭壇の一部を緑色の蔦がはい、組み合わされた白い岩の隙間から、草の芽が顔を出していた。
「よく来たね、ジュンナ」
待っていたのは、ジュンナを育てた〈森守りの媼〉だった。
本当なら、そこに待っているのは母なる木の思念体であるはずなのだが、ジュンナには母なる木が居ないから、代わりに母であったエルがそこにいたのだ。
「何をしたらいいの? 〈根切り〉と言ったって、わたしには切るべき〈根〉もないのに」
「そうだね。お前は、森の理から外れた命だ。森の理に従う必要はない。この儀式だって、本来お前がやらねばならないものではないのだ。だが、〈母〉との決別を選択できる齢になったお前に、お前にしかできないことをやってもらいたい」
「わたしにしか、できないこと?」
エルはうなずくと、ジュンナの手をとって、白い祭壇に近寄った。そして、ジュンナの手を祭壇に乗せた。
「これは、遠い昔、聖なるものの棺であり、祭壇であったもの。今は、すべての死の棺だ。ジュンナ、この棺を開けてはくれないか。この森は死の悲しみをすべて、これに封印して、同時に生の喜びを失ってしまった。幾度となく我々はこの棺を開けようとしたが、森の理に縛られた我々には、棺を開けること叶わなかった。森に育まれた我々は、森を裏切れないのだな。だが、森につながらぬお前になら……」
「そのために、わたしを育てたの?」
ジュンナの声に、非難するような響きはなかった。この森に再び死が訪れることを、誰もが望んでいることは分かっていた。それに、人とは違うあり方をした自分を、それでも愛してくれていることは分かっていたから。
まさか、とエルは軽やかに笑った。
「どうして〈根なし〉の無力な赤ん坊が、森の理を断ち切るものだと思う? お前を拾って、ずっと経ってからだったよ。お前にならできると気付いたのは」
ジュンナは眉根を寄せて、白い石材のつなぎ目を指でなぞった。側面に、他のつなぎ目よりも少し深いつなぎ目がある。棺の蓋と棺本体との境目だ。
「開けたら……どうなるの?」
「生と死が、あるべき形に戻る」
「それって、みんなが死ぬってこと?」
「生まれるということさ」
「なにそれ」
ジュンナはむっとして、エルをにらむような目で見た。
「生まれることと死ぬことは、同じことなんだよ。わたしも、お前も、この森も、すべてが死ぬために生まれ、生まれるために死ぬのだから」
エルはジュンナの手をとって、両手で優しく包みこんだ。
「わかんない。そんなの……」
手を振り払おうとしたジュンナに、エルはやさしく微笑みかけて、そうかもしれない、と言った。
「嫌ならばいいんだ。これはわたしの自分勝手なのから。でも、もしもこの先、お前が死を求めるなら、その力が自分にあることを忘れないで居てほしい」
少しの間、ジュンナは何も言わずにエルから目を放したまま、棺に触れていた。そして、小さくため息をつくと、まっすぐにエルを見た。
「いいよ」
エルは、目を見開いた。
「わたしはね、この森が好きよ。大きな木も、光が少ししか入らないこの明るさも。だけど、知ってる。みんな、この森のことを悲しいと思ってる。こんなにきれいなのに、悲しいって思ってるんだ。みんなが望んでいるんでしょう? これを開けたら、きっとみんなの悲しみは、喜びに変わるんでしょう?」
エルはゆっくりとうなずいた。瞳に涙が光っていた。
ジュンナはそんなエルの様子を見ると、困ったように微笑んで、瞳に涙を浮かべて棺の蓋に指をかけた。すうっと息を吸い込んで、それから力を込めて持ち上げた。
ぱらぱらと、白い石材のかけらが小さく落ちて、表面を汚した土がこぼれた。からめ捕るような蔦が、一つちぎれ、二つちぎれた。蔦が引きちぎられるたびに、エルは身震いした。
しかしジュンナは臆することなく蓋を持ち上げた。少しだけ持ち上がった蓋の下に、棺の中が見えた。太陽と同じ強い光が棺から漏れて、棺の蓋が地面に落ちる。光ははじけて、森中がまばゆい光に包まれた。
エルもジュンナも、何も言えないままぼうぜんと立ち尽くしていた。すると、何かがはじけるような大きな音が、それから小さな音が、あちらこちらから聞こえてきた。木の幹のきしむ音、枝の折れる音だった。
「木々が、死んでいく」
立派な幹に裂け目が走り、からんだ枝で周囲の木々を巻き込みながら、次々と木々が倒れて行った。地響きが際限なく続き、遠くから人々の悲鳴が聞こえた。押しつぶされないようにするのも、難しいくらいだった。
地響きが鎮まると、周囲の景色は一変していた。コケに覆われていた大地は、今や倒れた木々の幹に埋め尽くされ、木々の間にあった小道は見えなくなっていた。白い石の祭壇は、木に押しつぶされて砕けていた。空を覆う枝は消え、薄青い空が見えた。太陽があった。
「すごい……これが――」
何かを言いかけて、エルが大地に崩れ落ちた。
「〈媼〉!」
「ありがとう、ジュンナ……すまなかった……」
エルは、やっとそれだけ言うと、最後の息を吐いた。
動かなくなったエルの体は、枯れるように、しぼんでいった。倒れた木々の幹も、ほとんどが急速にその形を失いつつあった。まるで、引き伸ばされていた時を、一気に駆け抜けていくかのように。
「みんな、死んじゃったの……? 何も生まれないじゃない」
ジュンナは大地に付して、たまらない寂しさに震えた。涙が頬に光った。
かつて森であった場所を、静寂が包みこんでいた。遠くから聞こえていた悲鳴も、もう聞こえなかった。太陽の光だけがまぶしく大地を照らし、薄く残ったコケの緑がきらめいた。崩れ、色を失い土に還った幹の間には、まだ死の時を迎えていない老木だけが枝を伸ばしていた。
ジュンナは、もう森ではない場所を彷徨った。どこかに生きているものが、人がいるのではないかと、わずかに抱いた希望を頼りに、荒れた大地を進んでいった。しかし、人の姿はもうどこにもなかった。死者の体でさえ既に朽ちてその姿を失っていた。
わずかな老木と、大地に光るコケだけが、この場所に残された命なのだと分かると、ジュンナは大地にうずくまった。自分がしたことの意味に、涙が込み上げてきた。
と、不意に静寂を割る音が聞こえた。微かな音だった。
それは、大地を、朽ち果てた木々を割り、太陽の光に手を伸ばす新芽の音。今まで弱い光の中では姿を現わせず、土の中で眠り続けていた無数の種が、割れる音。それらもまた、止められていた時を駆け抜けるかのように、急速にその生を現したのだ。
だが、朽ちた大地に芽吹いた若い目が、急速に伸びてゆくことはなかった。誕生こそ駆け足であったが、その成長は穏やかなものだったのだ。
いつか、今残った木が倒れる頃には、芽吹いた木々が再び、その根の間に子を孕むようになるだろう。そして、ここは再び森になる。