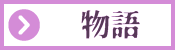どちらでもないということ
都市の中層に位置する複合娯楽施設、カリュオン。その最上フロアは軽飲食スペースになっている。広々とした空間に可動式のテーブルとイスが無数に置かれ、その間を給仕用の赤いオートマトンが行き交う。
フロアの端、曲面ガラス窓に近いテーブルを、ツェル、セヤ、メラン、チャルニィ、ヨーダスの五人が囲んでいた。
「いやっほう! ジャンクフード食べ放題いぇっす!」
「ちょっとチャルニィ、やめてください!」
その容姿にふさわしく最も大はしゃぎしているのは、最年少のチャルニィ。その隣に座るヨーダスは、注文端末を楽しげにいじくるチャルニィを止めようと、半ば悲鳴のような声を上げていた。
セヤとメランはそんな二人を見て、くすくすと笑っていたが、ツェルは面白くなさそうにため息を吐いた。
「なあに、ため息吐いちゃって。せっかくの休暇、もっと楽しんだら?」
「そうだよ!」
そう、今日は「せっかくの休暇」――毎日ほとんどの時間を研究施設の中で過ごす五人にとっては久しぶりの、完全オフ日だった。
「いや……」
ツェルは反応に困って、他のテーブルの方に目をやった。今日は世間的にも休日らしく、このフロアも大変にぎわっている。と、こちらを見ていた数人の大人たちが目をそらすのが見えた。
見るんじゃなかった。
仲間たちはいつにも増して楽しげだが、ツェルにとって施設の外は、いつも少し居心地が悪かった。自分がいかにも「普通じゃない」ってことを思い知らされるような気がして。
「あのねえ」
「何す――」
セヤは、暗い顔をしているツェルの右耳を引っぱって、無理やり視線を引き戻した。
「自称『普通』さんの、やることなすこと気にかけてたら、ハゲるよ?」
「え! ヤダ、脱ストレスしなきゃ!」
「メラン、あなたは平気なんじゃない?」
「そんな! セヤさん、なんかおススメないんですか、ストレス解消」
「そうだなあ、それなら――」
メランが大げさに反応したところから、二人の会話はヒートアップしだした。ツェルはそれをぼんやりと聞きながら、意識をテーブルの反対側に向けた。チャルニィとヨーダスは相変わらず言い争っている。主導権はすっかりチャルニィが握ったらしく、ヨーダスがほとんど無駄な努力をしているのが見てとれた。
普通、人は十五歳くらいまでには性別(性的に未分化な肉体が、男女二つの性のどちらかに分かれること)を済ませ、性を獲得する。それがこの社会の常識だ。だが、ツェルたちは成人年齢(十八歳)に達していながら、性別していない〈未性選択者〉だった。
〝全ての物質はある種の振動によって構成される〟という構成振動理論の提唱から約百五十年。それまで謎に包まれていた性別の原理も、五十年前には振動科学の視点から解明された。脳の器官が発する干渉振動が臓器の構成振動を書き変える。それが性別だった。
性別による急速な肉体の変化は、ときに苦痛をもたらす。肉体的にも、精神的にも。研究が進んだ今日では、そんな苦痛を和らげる抑制治療はごく一般的だ。そして、「性別しない」という選択肢でさえ、今や選択可能だった。
性の獲得に対して肉体的、あるいは精神的に大きな苦痛を感じる子どもたちは、昔から少なからず存在した。そんな子どもたちにとって、「性別しない」という選択肢は画期的なものだった。しかしそれは同時に、「大人にならない」という選択でもあった。
五人の中で最年長のセヤは二十四歳。最年少のチャルニィとヨーダスでさえ十八歳。全員が成人年齢に達していながら、身長は低く童顔で、外見的にはほとんど十二、三歳の子どもと変わりなかった。
性別を止めれば、肉体の成長も止まる。それが、自然に逆らうことのひとつの代償だった。
「恋は? 恋は効くのよ。恋をすると綺麗になるっていうし」
「ええー、それは流石に……て言うか、むしろストレスじゃないです?」
「むぅ、メランは恋しないの?」
「しないですよ! あたしたち未性なんですから」
「なによう。ほら、ツェルは? 好きな子とかいないの?」
いきなり話をふられて、ツェルは肩をすくめた。どういう話の流れか。
「……まさか」
「なあに二人とも。未性だと恋できないなんてそんなことないのよ?」
「セヤさんは特別ですよう!」
セヤは、五人の中では特別に、女性に近い容姿をしている。完全抑制治療の黎明期に抑制治療を始めたせいだとか。
未性でありながらどこか大人っぽい姿は、ツェルには少しうらやましくもあった。
「あら。わたしだって、好きでこんな体してるわけじゃないんだから。それに、恋愛するしないに性は関係ないでしょう。別に、遺伝子分け合った子どもを望むわけじゃあなし、好きになるかどうかってだけの話じゃない」
「そういうもんですかあ?」
「そんなもんよ。別に好き合えってわけじゃないんだし」
「えー。じゃあセヤさんは、どんな人が好きなんです?」
「むぅ、そうだなあ――」
二人の会話に耳を傾けているうち、ツェルは次第に居心地の悪い思いがしてきた。この会話に加わっていたいとはあまり思えない。かといって、チャルニィとヨーダスの、半ば取っ組み合いのような会話に混ざる気もない。
でも黙って聞いていれば、またすぐに会話にまきこまれてしまいそうだ。
「すぐ戻る」
ツェルはそれだけを誰にともなく口にして、席を立った。
半ば逃げるような気持ちで足早に歩き出したものの、少しもしないうちに、ツェルの脳裏には「後悔」の二文字が浮かんだ。家族連れなどでにぎわうフロアを、たった一人で歩いていると、周囲の視線が一層刺さる気がした。
大半の視線はこちらに向いていない、向いていても自分を見てはいない。それを理解はしていても、心がついてこない。そんなツェルを、メランならいつも「自意識過剰」と笑うのだが。
長年の性別抑制による副作用を抑えるため、ツェルたちは常に耳や手足に装具をつけている。そのせいで、未性選択者かどうかは見ただけで分かる。
未性という選択肢の存在自体は知られ始めていたが、未性選択者となると未だに珍しく、異常、不快なものと見るものも少なくない。ツェル自身、完全抑制治療をしていると周囲に知られた最初のときは最悪だった。友人だと思っていた人たちの態度が一変したことは、今にして思えば全てがバカバカしくて笑える。
十五になって、性別研究の一環で構科研(構成振動科学研究所)の関連施設で生活し始めてからは、「普通じゃなさ」に苦しむことは少なくなった。周囲の人間は同じ境遇のものか、理解者が多かったからだ。休みの日にこうして外に出ても、仲間といればそれほど苦には感じなくなった。
だが、他人ばかりがごった返す場所で、こうして一人でいると未だに寒気がした。
そんなことを考えるうちにフロアの中央まで来ていた。楕円形の調理区画との境界の壁際。そこは広い通路になっていて、とりわけ昇降機から離れた場所は人が少ない。ツェルは柱の陰にもたれかかり、深く息を吐いた。ガヤガヤと響く無数の声、笑い声を耳触りに感じて、耳をふさいでしまいたい気持ちを抑えて眼を閉じた。息を深く吸い込む。
誰も自分のことなど見ていない。ただそこにいるだけ。
と、そのとき。不意に服の裾を誰かが引いた。眼を開けるより先に、反射的にその手を払いのける。
「なんだ――」
噛みつくように声をあげかけて、目の前の姿に言葉を飲み込んだ。そこにいたのは幼い子どもだった。恐らく十歳以下。
その子どもは、払いのけられた手を胸の前で抱えるようにして立ちすくんでいた。ツェルもまた唖然として、ほとんど睨みつけているような眼差しで子どもを見た。
同じ子どもの範疇だと判断して接触してきたのだろうか。それとも、もう分かっているのだろうか。とにかく、いきなり拒絶されて凍りついたのだ。そう理解して、ツェルは意識的に表情を緩めた。
「どうした」
「……ママ」
子どもは、おずおずと口を開いたが、一言それだけ言ってうつむいてしまった。
「なんだ……迷子か?」
ツェルの言葉に顔を真っ赤にしながらも、子どもは力強くうなずいた。やや悔しげな表情。いい歳してはぐれたことが恥ずかしいのだろうか。
「端末は?」
これくらいの歳の子どもなら、自分の携帯端末くらい持っているものだ。それなら自力で何とかできそうなものだし、少なくとも親の方から子どもを見つけられるだろう。
子どもは一瞬言葉に詰まって視線が揺れた。それから、意を決したようにツェルの目を見つめて答えた。
「なくした」
ツェルは天を仰いだ。失くしたとなるといろいろと面倒には違いない。今すぐ親を呼び出すこともできないらしい。さっさと警備マトン(警備用オートマトン)にでも引き渡したいが、警備マトンが迷子対応をしているのかすら、ツェルには良く分からなかった。
「お前、名前は」
「エレ」
「じゃあ、エレ。とりあえず警備マトン探せ」
右手で追い払うようなしぐさをすると、うるんだ瞳がツェルの視線をがっちりとらえた。「一人で行けって言うのか」と訴えかける眼差しだ。
他人と面倒に関わるのはごめんだったが、子どもは嫌いではなかった。大人と比べれば、好きと言ってもいいくらいに。
「……一緒に探すか」
ツェルがほとんど唸るような調子でそう口に出すと、エレはぱあっと笑顔になって歩き出した。
「なんてガキだ……」
給仕マトンは円滑な食品運搬に特化し、トラブルに対する柔軟な対応は――基本機能としては持っているはずだが――期待できない。警備マトンの方が、トラブル対応を専門とするだけに迷子対応向きには違いない。とはいえ、警備マトンをこちらから探しにいくのも骨が折れそうだった。
エレの後をついてテーブルの間、人ごみの中を歩きはじめると、ツェルは再び徐々に気分が悪くなっていくのを感じた。だが、自分より圧倒的に幼い子どもを放り出して自分だけが逃げるのは、違う意味で気分が悪い。目の前のことにだけ集中しようと、ツェルはエレに話しかけた。
「なあ。お前、なんではぐれたんだ」
エレは歩みを少し緩めたが、答えなかった。横に並んで表情を見れば、その不満げな口元は悔しいというよりはむしろ、腹を立てているように見えた。
「ケンカでも、したか」
ぼそりと言うと、エレははっとしてツェルを見、立ち止まった。
「……ママが悪いんだもん。何も、分かってない」
一瞬、その顔が泣き崩れそうに見えて、ツェルはぎょっとした。低く絞り出すような声は、わずかにかすれていて、
「そうか」
ツェルはそれ以上、何も言えなかった。
何も知らない癖に、分かったようなことを言うのは嫌いだ。赤の他人の事情を聞きだすのも違う気がする。どうせ、自分には何もできないのだから。
だが、このまま立ち尽くしているのも辛い。そんなことを思っていると、後ろから突然、叫ぶような声が飛んできた。
「エレ! なにやってんの、探したのよ!」
声に振り向いたエレの顔に、安堵と恐怖がほとんど同時に浮かんだのを見た。
声の方を見ると、そこに女が立っていた。母親だろう。こちらは安堵よりも怒りの表情の方が目立つ。その手には子ども向けの携帯端末が握られている。エレは失くしたと言っていたが、ケンカの最中に投げつけでもしたのだろうか。
「ママ……」
これで役目も終わりかと安心しかけたところで、エレのすがるような視線と目があった。
「えっ?」
とっさに母親の方に視線を向ける。
母親はというと、我が子の視線を追ってツェルの姿を認め、それから我が子の方をキッと睨みつけた。
「あんた、この人が何か分かってんの!」
その激しい口調に、ツェルは血の気が引くのを感じて、動けなくなった。
未性嫌悪者。
子どもの姿をした大人、どちらでもないもの。そういうものに嫌悪感を持つもの。面白がったりバカにしたりするものたちだって、多かれ少なかれ違和感や嫌悪感を持って、ツェルたちのことを見ている。そんな人間が世の中にはたくさんいることくらい、ツェルは十分理解していた。
だが、はっきりとした嫌悪感を直接向けられる心の準備は、全くできていなかった。
母親の言葉の矛先はほとんどエレの方に向いていた。それでも、自分が刺されているような感覚がじわりと押し寄せて、ツェルは二人の良い争いを、なすすべもなく見つめることしかできなかった。
「やめてよママ! この人は、この人は――」
「未性じゃない! なんでこんなやつと、一緒に」
「助けくれたの!」
「なんであんたは、そうやって……。あんたもこんなふうになりたいっていうの!」
ヒステリックに叫ぶ母親が、今にも泣きだしそうな顔をしていることにふと気づいた。同時に、二人のこの感情的な言い争いが、どうしようもないくらい人目を引いているのに気づいて、ぞっとした。
「この人の何が悪いの? なんで、どちらかにならなくちゃいけないって言うの? ママはわたしに幸せになってほしくなんかないんだ!」
「なんでそんなこと言うの! 幸せになってほしいから言ってるに決まってるじゃない! わたしは、あなたをそんなこと言う子に育てた覚えはありません!」
母親の鋭い言葉が刺さった。エレは息を飲んで、開きかけた口をつぐんだ。悔しげな表情で顔をゆがめると、踵を返し走り出す。
と、その腕を誰かが掴んだ。
「何、やってるの?」
そっとエレの動きを止めながら、ツェルに対して静かに尋ねたのはセヤだった。
「なんで――」
「ツェルが『すぐ』戻ってこないから、探しに来たんだけど」
確かに「すぐ戻る」と言って席を立ったのだった。それから、どれくらいの時間がたっていたのだろう。
「なんだか、変なことになってるわねえ」
エレは戸惑いの表情で、エレの母親は恐ろしいものでも見るかのように、セヤの姿を見つめている。一瞬の後、我に返った母親はヒステリックに叫んだ。
「エレを離して!」
セヤはすぐに掴んでいた腕を離した。母親はエレに駆け寄ると、まるで我が子をかばうかのように抱きしめた。その様子をセヤはただじっと見つめていた。何を考えているのか分からない顔で。
それから、ツェルが再び沈黙に耐えきれなくなった頃、セヤはあくまで穏やかに、ひどく静かな声で語りかけた。
「わたしたちのことを、肯定的に受け止めろとは言いません。でも、お子さんのことは弾かないであげてくれませんか。一緒に、考えてあげてくれませんか。最後に何を選ぶとしても」
セヤはいつから見ていたのだろう。一部始終を見ていたのだったら、もう少し早く助けてほしかったのだが。
「どうせ……子どもも持てないあんたたちに、何が分かるっていうのよ」
母親は顔をあげずに吐き捨てた。
一瞬、セヤの瞳にひどく悲しげな影がよぎった。けれど、続けた言葉は変わらず穏やかだった。
「分かりません。でも、未性がただ不幸なだけの存在じゃないって、それだけは分かっています。ねえ、そうでしょうツェル?」
明るい調子で同意を求められ、ツェルは躊躇いながら、小さくうなずいた。
普通に、男か女かどちらかになっていたとしても、もしかしたら不幸ではなかったのかもしれない。どちらでもないからこそ、気分の悪い思いをすることだってある。
だけど、「どちらかになる」ということは「自分でなくなる」ことだという確信があった。それに、今の仲間たちとの暮らしに不満はない。
「少なくとも、今のおれは……不幸じゃないです」
ツェルの答えにセヤは嬉しそうにうなずいて、母子に視線を戻した。
「今はまだ無理でも構いません。でもいつかきっと、一緒に考えてあげてください。本当に幸せな道を。……必要なときは、いつでも構科研の相談窓口に連絡してくださいね」
最後の言葉はきっと、母親とエレの両方に向けて言ったのだ。
それから、セヤはツェルに目で合図するとその場を離れた。
「良かったんですか? あれで」
「どうかしら。まあ、事情を何も知らないくせに、差し出がましいことを言っちゃったかなとは思うけどね……。でもあのままじゃ、ツェルは当分動けなかったんじゃない?」
セヤは考え考え口にしていたが、最後に声色を明るく変えて微笑んだ。
ツェルは答えに詰まった。人の敵意や悪意に近づくと、その場で釘づけになって逃げ出すタイミングを見失うのは、今に始まったことではない。それはセヤも承知している。
「……って、いつから見てたんです?」
「あの母親が子どもを見つけたところから、かな」
セヤはいたずらっぽく笑ってみせ、
「さーて。気にしても仕方のない話はやめ! それより、さっきの話だけど。気に障ってたならごめんなさいね」
「さっき……?」
「メランと話してた『恋バナ』のこと。嫌な思い出にでも触れちゃったかなって」
「『恋バナ』? ……ああ、いえ、嫌だったわけじゃなくて――」
ツェルは言いかけて言葉を飲み込むと、話題を少しずらした。
「セヤさんは、恋してるんですか」
そう尋ねると、セヤは少し意外そうな顔をした。
「ん? ツェルでもこういう話に興味あるんだ。どちらかと言うとキライなのかと思ってた」
「別に、嫌いなわけじゃないです。ノリで、笑い話みたいにするのが、少し……苦手で」
「そっか。ツェルは内側を大切にしたい方だものね。うーん、好きな人はいるのよ」
「男性の?」
「内緒。でも、男を好きにならなきゃいけないわけじゃないでしょう? 女を好きになっても、未性の子を好きになっても構わない。もちろん、男を好きになっても、ね。わたしたちほど、それが自由な存在ってないんだから」
「自由?」
五人の中で最年長であるセヤは、だからこそ最も長く好奇の目にさらされ、恐らく辛い思いだってツェルよりも多くしてきたはずだ。なにより、未性としても肉体的に中途半端な存在であるセヤが抱えたはずの苦悩は、想像を絶する。
そんな自らを「自由」と言えることが、ツェルには少し不思議だった。
「男と女、そのどちらでもないということは、ある意味、最初から『普通』に縛られてない分、自由なんじゃない?」
セヤはこともなげに言ってみせた。ツェルは少し圧倒されながら、口を開いた。
「さっきの『幸せ』って話でも思ったんですけど……今のおれたちのことを、『幸せ』とか『自由』だなんて、躊躇いもなく言ってしまえるのは、セヤさんくらいじゃないですか?」
「そうかしら? いつか世界が本当に平和になって、技術がもっと進んだら、わたしたちはきっともっと自由になる。でも、今だって精神は充分に自由なのよ」
セヤの言葉に、なんとなく納得できてしまいそうな自分がいて、ツェルはもっと不思議な気持ちになった。自由なんてものは信じられないと思っているはずなのに。
セヤは本心からそう言えるほどに、迷い、考え、そして答えを出したのだろう。それとも今なお、自分自身に言い聞かせるために、そう口に出しているだけなのだろうか。
「さあて。そろそろ戻りましょっか。わたし、あなたを探しに出てきたんだった。みんな心配……はしてないかしら。今頃、それどころじゃないかも」
「へ?」
「もう、ツェルもセヤさんもおーそーいっ」
戻ってきたツェルたちの姿を見つけて、チャルニィが叫んだ。続けて、メランが困り果てた様子でテーブルの上のものを指す。
「ふたりとも見てよこれー」
「あらあら」
「まさか……全部、一人で食うつもりだったのか」
テーブルの上には、ゆうに十人分はあるかという軽食、パフェの類などと、その残骸があった。
「これでもみんな頑張ったのよ。でも二人もいないしどーにもならなくって」
メランがため息混じりに告げた。食事はまだ半分近くがほとんど手付かずで残っている
「だから、やめてくださいって言ったじゃないですかあ。こんなバカみたいに頼んで、大半残して帰ったんじゃ、構科研に苦情きますよ。未性の信頼ガタ落ちですって」
疲れ果てた様子のヨーダスが、チャルニィをじとっと眺め、
「だってぇー食べたかったんだもん」
チャルニィが小さい子どものようにふくれっ面をしてみせた。
「わたしもそんなには食べられないわよ? でも、残していくのも忍びないわねえ」
なんてことを言いながらセヤはすっと席について、パフェをひとつ引き寄せ、「では、いただきますっ」と呟くと、いかにも美味そうに食べはじめた。
ツェルは少しの間立ち尽くしたままその様を見つめていたが、メランに促されて席に着くと、盛大にため息を吐いた。
「後始末は、自分でやれよ」
そう低く唸ってから、チキンののったプレートを手に取る。
「うう……ごめんなさい」
チャルニィはそう言いつつ、しぶしぶといった様子で手元にあるフィッシュ&チップスをつまんだ。もうずいぶん食べたのだろう。いかにも食欲がなさそうだ。
「よっしゃー。わたしたちも片づけるよ!」
奮い立たせるように声をあげたメランの、その声の大きさにツェルは少し身をすくめたが、周囲をうかがうのは、ひとまずやめた。今はそれどころではないし。
それに、不幸ではないと言ったあれは、嘘ではなかったと思う。こうやって仲間と過ごすことができるのは、幸運だとさえ思える。
だったら。こんなときくらいは、外側の嫌な現実から逃げてみてもいいんじゃないか。
「いただきます」
冷めかけたチキンは、それでも存外美味かった。