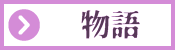銀の地平
世界っていうのは、黒い空と灰色の大地、ただそれだけだと思っていた。
「手が……届きそうだ」
灰色のごつごつした大地に寝転がって、セキは漆黒の空に手を伸ばした。白地に赤く細いラインが幾筋も走るぴったりとした与圧スーツに覆われた手が、砂粒の星をさらう。
白い星、赤い星、それから青い星。その中でひときわ大きく輝くのは、かつてヒトが大地と呼んだ星。青く淡い光を放つ星だった。
あんなものにこの大地がとらわれているなんて、にわかには信じられなかった。けれど、そういうものだということはだれもが知っていた。
「今日はもう、このままここで寝てしまおうか。きっと、誰も気にしないから」
セキはそんなことを呟いた。誰に言うわけでもなく、ただなんとなく口に出してみた。
ここは、街の外殻からかなり離れた場所にあるクレーターの底だった。誰も来ない、暗く静かな場所だった。危険な隕石、ゼロ気圧や不可視光線なんていうもの一切から守られた街から出てくるようなやつなんて、だれひとりいない、そういう場所。少なくともセキの知る限り、ここに来る人間はセキだけだった。
「街の人間は狂気の沙汰じゃないって言うんだろうな」
セキは与圧ヘルメットの中でほくそ笑んだ。
移民時代のスーツで街の外に出ているだけで、白い目で見られるような世の中だった。本来、与圧スーツというものは安心を買いたいやつだけが持っている保険にすぎなかったから。万が一、街の外殻が傷ついて街の空気圧が下がったときに、シェルターに駆け込まなくて済むように用意してあるだけのもの。それでわざわざ危険な街の外に出るやつなんていない。それが常識だった。
つまり街の外に出る人間は存在しないということで、街の外に出歩くためのスーツは存在しないということだった。
「だったらこれを使うしかないじゃないか」
他人になんと言われようとセキはこのスーツで外に出たし、伸縮性のあるぴったりとした白いスーツをセキは気に入っていた。幸い、かつて人間がこの街を築くために危険に身をさらしていたときから、スーツの性能は落ちていなかった。
街に帰ろうかどうしようか、セキがしばらく考えていると、何かが空を横切った。白っぽいゆがんだ形の何かが。
初めは星だと思った。
空のひときわ明るい星、この星系の恒星が青い星をとらえているように、青い星がこの星をとらえているように、この星もときどき小さな星をつかまえる。
あれもそんなものかとセキは思ったけれど、不意にその星はふたつに分かれ、ひとつがはそのまま空を行き、ひとつは空を落ちていった。
「隕石? いや、そんなものじゃ……」
立ち上がって落ちてくる星の行方を追うと、星はあまり遠くないところに落ちていく。
セキは星を追いかけた。落ちてゆく星が気になったのだ。それから少し離れたクレーターに隠れて、様子をうかがった。
星は隕石みたいにぶつかるのではなくて、ゆっくりと着地した。それからまるで家みたいに扉が開いて、なかからヒトが出てきた。白い服を着てまん丸のヘルメットをかぶった、ずんぐりむっくりした背の低いふとっちょがひとり、それからもうひとり。
「ヒト……?」
セキの中にふつふつとわき上がっていた好奇心の中に、恐怖心が混ざりこんだ。
空から来たのは、ヒトなのだろうか。それとも、ヒトの形をしたもっと別のものだろうか。確かにあれは人間によく似ていた。ひとつの頭とふたつずつある手足。しかしヘルメットの中身は光の反射で見えなくて、セキには空から降ってきた彼らが得体の知れないもののように思えた。
「だけど、ここまできたらもっと……。うん、ここで帰ったって、どうせ街のやつらは知らんぷりを決め込むんだから」
街の人間は殻にこもって外のことには目もくれない。外のことを気にかけているのは天文観測部くらいだった。彼らでさえただ隕石の落下予想をたてるだけ。街に落ちないものになんて興味は持っていなかった。
だれにも頼れない。セキは自分を奮い立たせると、クレーターから這い出して、ふたりのずんぐりむっくりに近づいていった。
ふたりはセキに気がつくとこちらを指さし、身振り手振りで何かを言った。だけど、真空は音の一切を伝えてはくれなくて、セキは不満げに自分のヘルメットをつついた。
「周波数が分かればなぁ」
ヘルメットには通信機がついている。ずんぐりむっくりたちも、互いに意思疎通ができているように見えるので、彼らのヘルメットにも通信機があるに違いなかった。
「でも、どうせ言葉が通じないか」
セキはしゃがみこむと、地面の砂に〈SEKI〉と自分の名前を指で書いてみた。
「セキ」
セキは文字を指し、それから自分を指した。
ふたりのずんぐりむっくりは地面の文字をしげしげと見て手足をばたつかせると、セキを指さし何かを言い合った。
ふたりの意思を推しはかろうと、セキはふたりをしげしげと眺めた。そのとき、ヘルメットの中に顔が見えた。人間の形をしていた。姿はずんぐりむっくりしているくせに、顔は思い描いていたものより細かった。
「……スーツが膨らんでるんだ」
はるか昔、与圧スーツというのは今よりずっと動きにくいものだったという話を、どこかで聞いたことがある。彼らもそれと同じようなスーツを着ているのだろう。
「過去からの訪問者、か」
ずんぐりむっくりの片方がしゃがみこもうとしたけれど尻もちをついて、もうひとりがひっぱり起こした。やっぱり、スーツが膨らんでいるせいでうまく動けないようだった。
「ねえ、きみたちは……」
セキは何かを伝えたくて、触れたくて、手をふたりの方に伸ばした。
けれども、ふたりはセキの手から逃れるかのように身を引くと、何かを伝えようとするのもあきらめたようで、あの落ちてきた星の方へ跳ねながら戻っていってしまった。
「逃げられちゃったな」
セキは、またふたりが出てきてくれないだろうかと思って、それからしばらく星を見つめていたけれど、結局ふたりは出てはこなかった。
それから星の底が火をふいて、星は空にあがっていった。どんどんあがっていくと、空でもうひとつの星が待っていて、ふたつの星は再びひとつになった。
そうして星は空を横切って、見えなくなった。
それから、セキは来る日も来る日も空を見上げた。
「また、来ないかなあ」
けれど、あの星が黒い空を横切ることはなかった。
そうして、何も現れないまま何年もの月日がたっていった。
だれもがセキに、いいかげんそんな幻想を追いかけるのはやめろ、街の外に出るのをやめろと言った。あの日落ちてきたものに関心のある人間はやっぱりだれもいなかった。街の人々はもはや、街の外殻の向こう側のことになんて興味がないことをセキは分かっていた。
けれどセキには他の人間と同じようにふるまうことなんてできなかった。青い星にいた頃のことなんて、もう何も覚えていないくせに、いまだにまがいものの青い空を掲げている街の天井を見るのが嫌いだった。本物の黒い空の方がずっと好きだった。
「本物は、本物っていうだけでこんなに綺麗なのに」
だから、セキはその日もいつもと同じように黒い空を見上げていた。
「あっ」
何かが空を横切った。けれど、セキは見つめてそれから小さく首を横に振った。
「違う」
それは、あの日の星より小さかった。そして、それは落ちてきた。小さな隕石のように。だけどずっと優しく。
立ち上がって行方を追うと、銀色の地平線に動く何かが見えた。銀色で、金色の何か。近づいてみると、それ四角い箱にまるいパラボラとキャタピラがついた機械だった。
「こんなもの……。もう、きみたちはここにはこないのかい?」
セキは愛でるように機会を見つめた。そして不意に悲しくなった。
「ぼくは、きっときみたちにまた会いたかったんだ。だけど、ぼくは……ぼくは待ってただけだった。街のやつらとなんにも変わりはしないんだ。この地面から離れようともしない。……ぼくは本当は、きみたちに連れていってほしかったんだ。きみたちの世界へ。こんな……こんな銀色の地平じゃなく、もっともっと素敵な世界へ。この黒い空へ」
ひとつ口にしてしまったら、あとからあとから零れ出た。セキは気づいてしまった。自分でも気づいていなかった、気づかないフリをしていた渇望に。
ここではない、どこかへ――。
それで何かが満たされるなんて信じてはいなかった。それでもセキは、あのふたりのずんぐりむっくりの世界へいってみたかった。自分の立っているところよりも遠くの事柄への興味をまだ失っていない人間のいるところへ。
それでいて、結局セキは最後にはあの街へ帰ることしかできなかった。どこか見知らぬ世界へいってしまうことなんてできなかった。
「きみたちも、やっぱり自分たちの世界から離れてしまうことなんて、できなかったのかな……。なあ、おまえはさ、どうしてここに来たんだよ」
セキはかたかたと地面を進む機械に触れようと手を伸ばし、触れる寸前で手を止めた。
「また逃げられちゃうかな」
しかし機械は動きを止めたりはしなかった。セキの存在に気がつかないかのように、でこぼこの大地に揺られながら動きつづけた。そして、そのままかたかたとセキの横をすり抜けて、そのまま灰色の地面を進んでいった。
セキはゆっくりとその動きを追うように振り返ると、そのあとは釘付けにされたように動けなくなって、ただひたすら遠くなっていく機械の姿を見送った。
「また、会えるよな」
動くものが見えなくなった頃、やっとそれだけを言うとセキはへたり込んだ。そして大地に背をつけ、黒い空に手をかざした。
世界は、黒い空と灰色の大地、ただそれだけだ。この空の光のどこかに、そうではないところがあるのかもしれない。自分の知らない世界が。
セキは星をさらうように空をすくった。昔は手に届きそうだった星々が、なんだか遠く見えた。
「待っていてもいいだろうか。ぼくは街のやつらと同じになってしまうかもしれない。いや、きっともう同じだ。それでも……」
それからも、セキは毎日のように街の外で銀色の地平線と黒い空を見つめ続けた。時折、大地をうがつ隕石の中に金色や銀色の機械が混ざっていることがあった。
けれど、あのずんぐりむっくりのヒトは姿を現さなかった。
そうして、いつしか街の外にあらわれる人間はいなくなっていた。